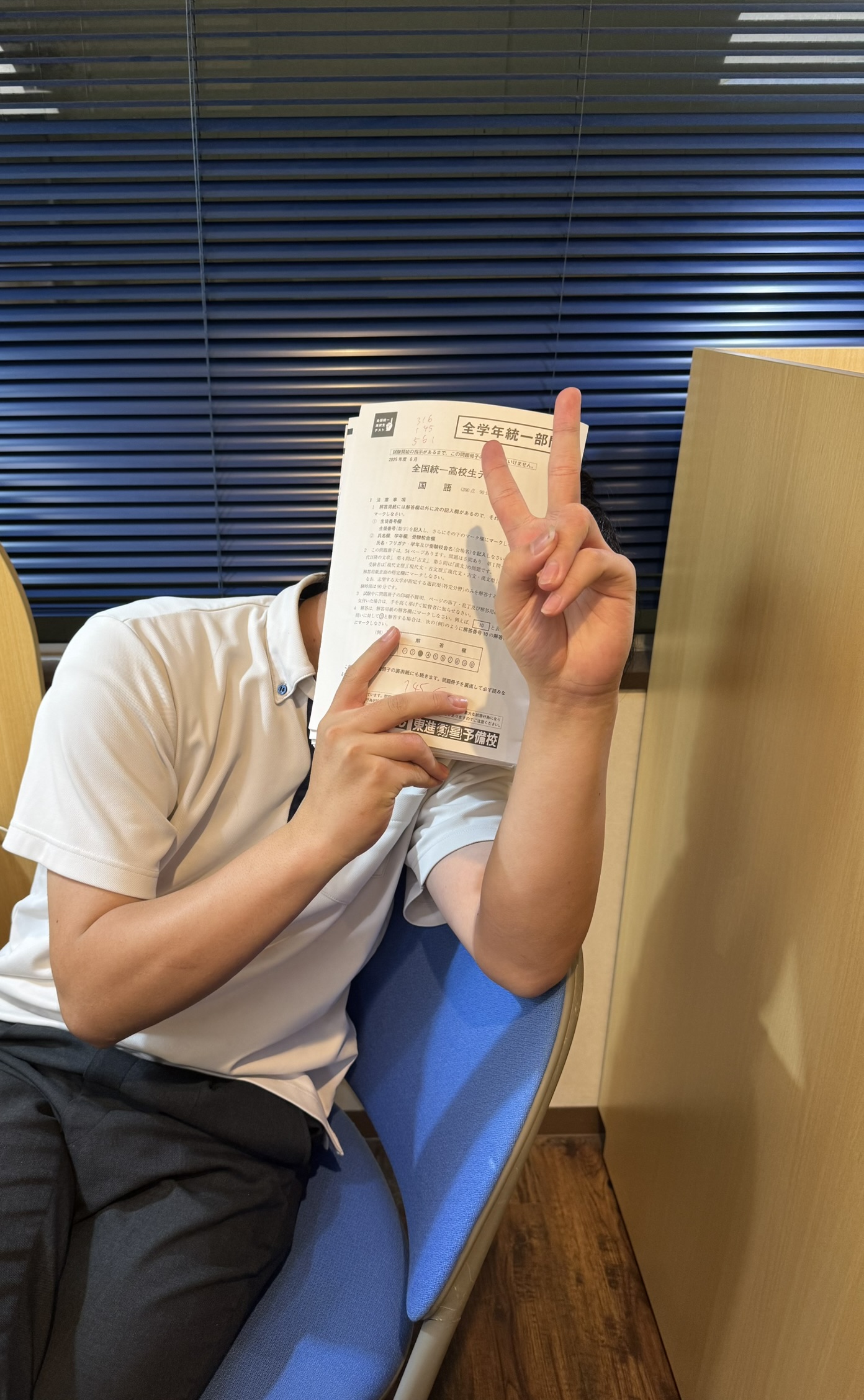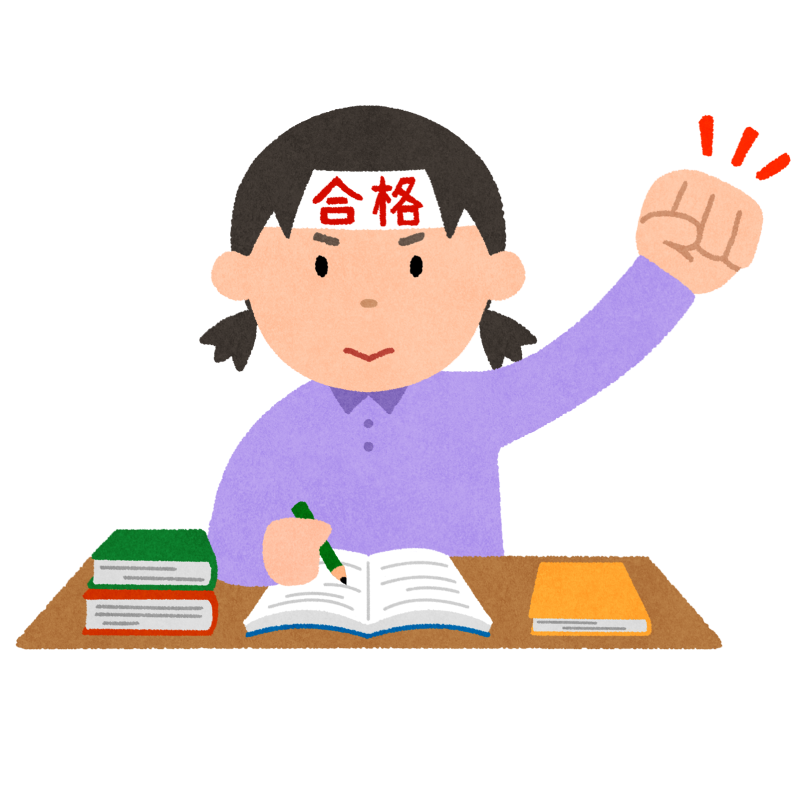こんにちは!
日々たくさんの子どもたちと接する中で、「勉強に前向きになれる子」と「なかなか動き出せない子」の違いを目の当たりにします。
そのたびに感じるのは、やはり家庭の力――
中でも**親御さんの「マインドセット」**の影響はとても大きい、ということです。
この点については、日頃から塾長とも深く話し合い
「子どもの成長のカギは、家庭の空気と親の姿勢にある」
という認識で私たちは一致しています。
■ 子どもを責める前に、“自分”に問いかけてみる【他責はNG】
成績が思うように伸びない。
家でまったく勉強しない。
反抗的な態度をとる。
そんなとき、つい「うちの子はやる気がない」「勉強が苦手なんだ」と、子ども自身の性格や能力のせいにしてしまいがちです。
でも、そこで少しだけ立ち止まり、こう自分に問いかけてみてください。
- 自分の声かけは、どんなトーンだっただろう?
- 「なぜできないの?」ではなく、「どうしたらできるか?」という関わりができていたか?
- 忙しさや不安から、子どもの気持ちを置き去りにしていなかったか?
これが、私たちが大切にしている“自責思考”です。
■ 「自責」とは、決して“自分を責める”ことではありません
誤解のないようにお伝えしたいのは、自責思考とは「自分が悪い」と落ち込むことではありません。
そうではなく、自分の関わり方にも何か改善できる点があるかもしれない
子どもが変わらないなら、まず自分が変わってみよう
と仮説を立て、行動してみる姿勢のことです。【物事は全て仮説検証です】
これは教育において最も建設的で、愛に満ちたアプローチです。
実際、塾長とも「本当に変化する家庭ほど、この“仮説と思考の柔軟さ”を持っている」と、たびたび話題になります。【上手くいくまで、軌道修正】
■ 「接し方を変える」と、子どもは驚くほど変わる
「勉強しなさい」と言う代わりに、
「今日何かできたことあった?」と聞いてみる。
「何でできないの?」と怒る代わりに、
「ここはどうやったら分かるようになるかな?」と一緒に考えてみる。
たったそれだけの言葉の違いでも、子どもの反応がガラッと変わることがあります。
これは私たち塾でも日々経験していることで、
関わる大人の“前提”や“スタンス”が変わると、
子どもはちゃんとそれを受け取り、行動も変えていくのです。
■ 「やらせすぎ」も逆効果。バランスが大切です
ここで重要なのが、過干渉の問題です。
「やらせなきゃ」「全部サポートしなきゃ」と親が先回りしすぎてしまうと、子どもは自分で考える力や、挑戦する力を育てる機会を失ってしまいます。
親が何でも決めてしまい、声をかけすぎることで、
子どもが「どうせ言われるからやる」あるいは「言われないとやらない」という思考になってしまうのです。
実は、過干渉は子どもの成長を妨げる【ストレスになる】ことがあるのです。
大人が「見守る勇気」を持つこと。
そして「子ども自身の力を信じる姿勢」を示すこと。
それが、自責思考の中でも非常に大切な要素だと私たちは考えています。
■ 私たち大人も、変わり続ける存在でいたい
子どもが伸び悩むとき、
「子どもが悪い」と考えるのではなく、
「何か別のやり方があるかもしれない」と視点を変える――
この柔軟さと前向きさが、子どもたちにとって何よりも大きな励ましになります。
■ 最後に
子どもが変わる瞬間というのは、実は“親が変わったとき”と重なることがよくあります。
子どもに期待するのではなく、
子どもに任せきりにするのでもなく、
親自身が「何ができるか」を考えて動くこと。
そして、必要以上に手を出さず、信じて見守ること。
これが本当の意味での“子育て”であり、
そして私たち塾が大切にしている家庭との「共育(ともいく)」の姿勢です。
ご家庭と塾が同じ目線で、同じチームとして子どもを支えていければ、こんなに心強いことはありません。
これからも、一緒に「前向きな自責思考」で、子どもたちの未来を育んでいきましょう!